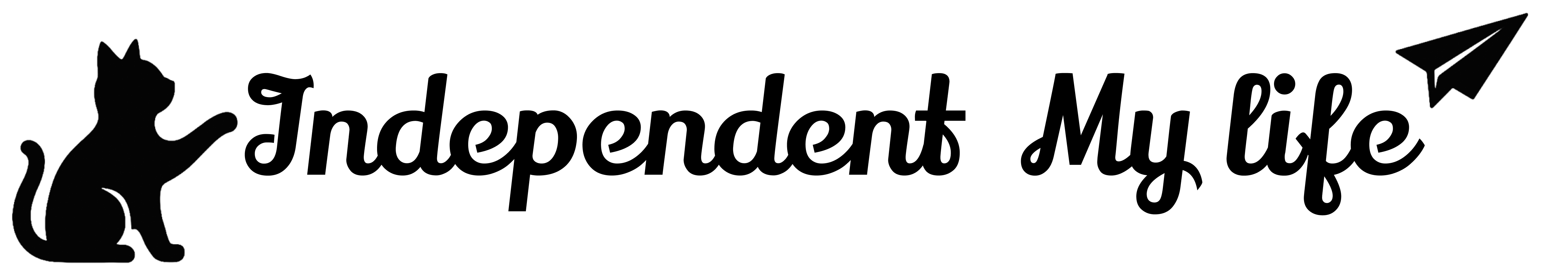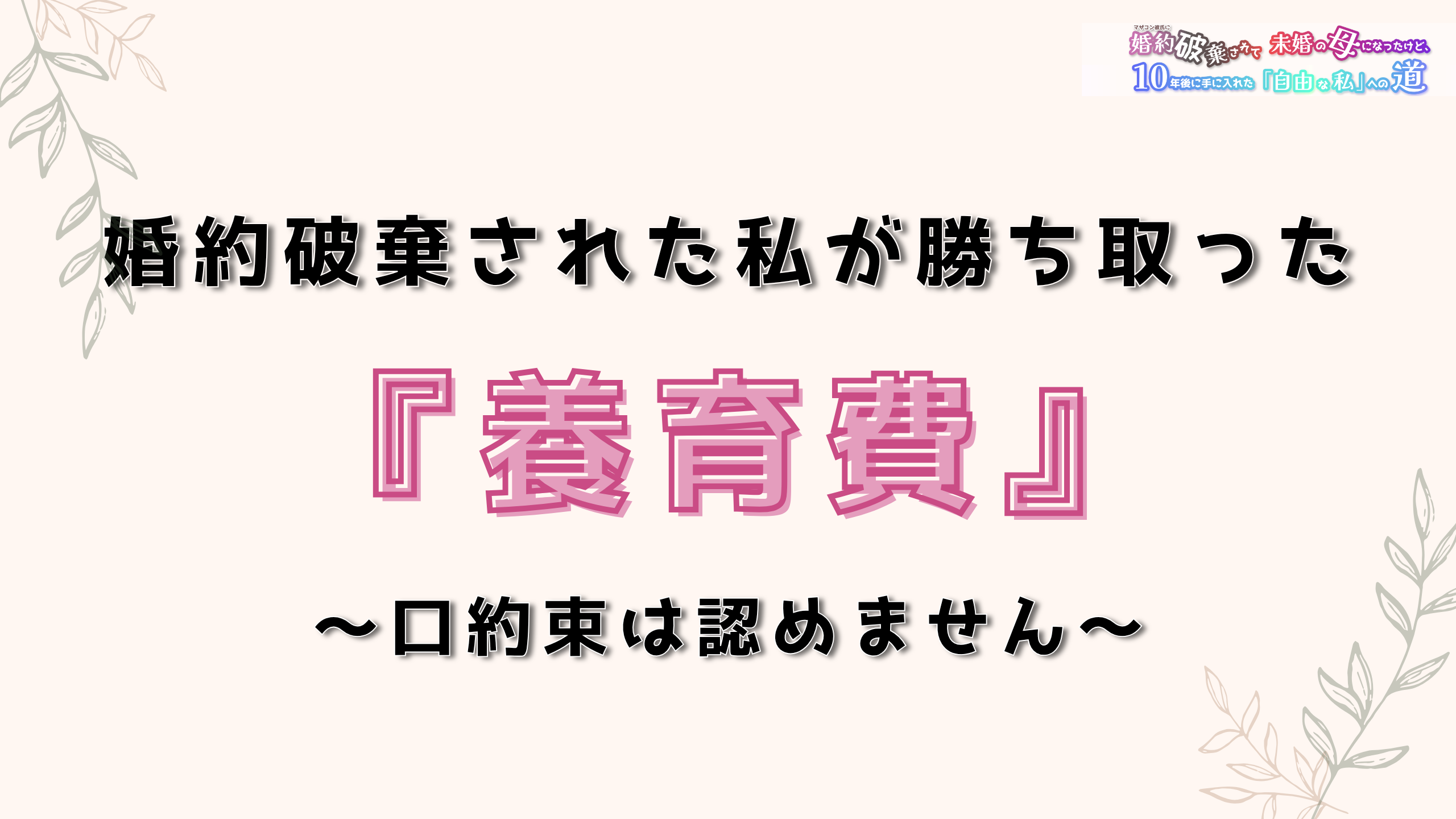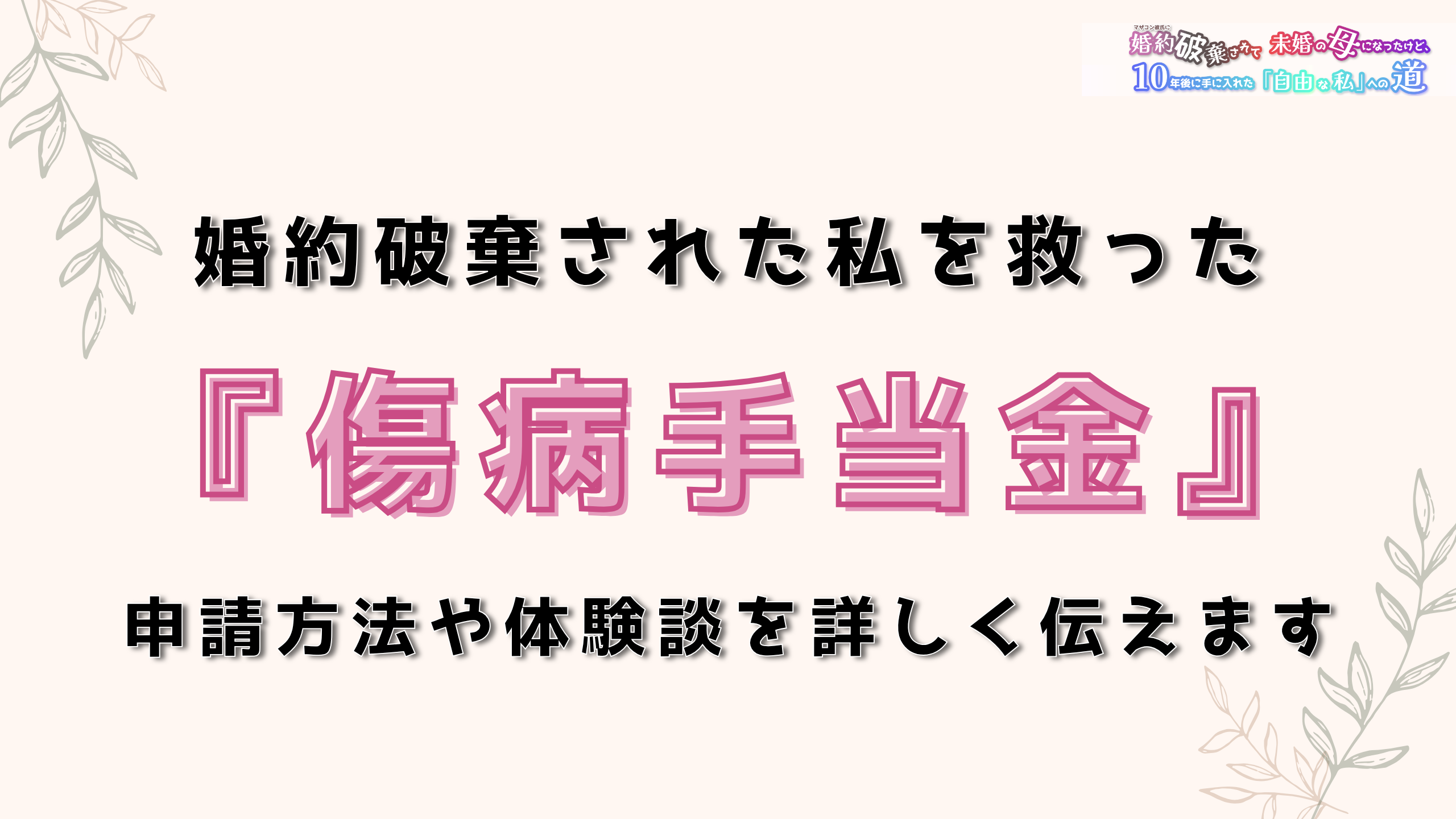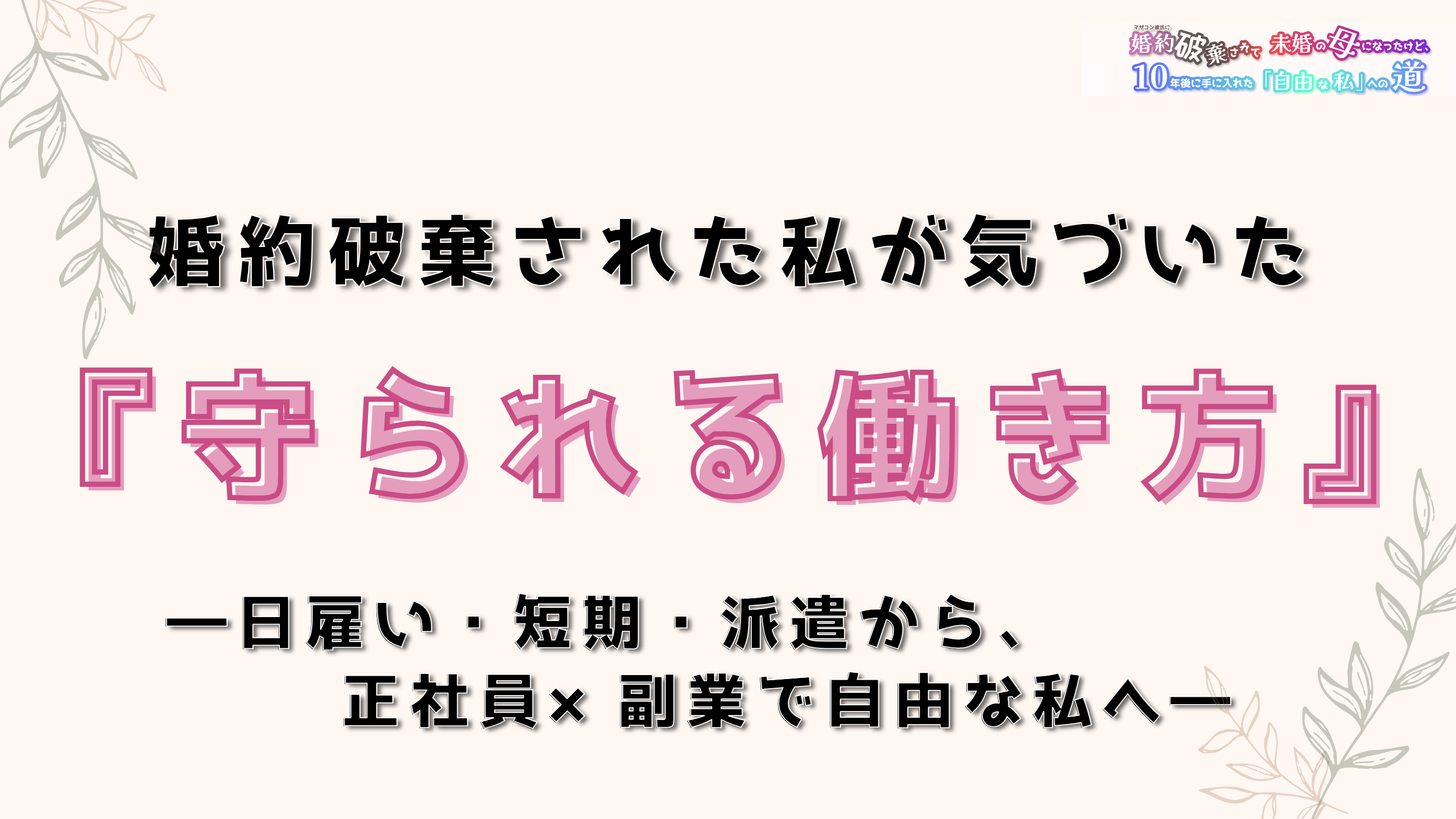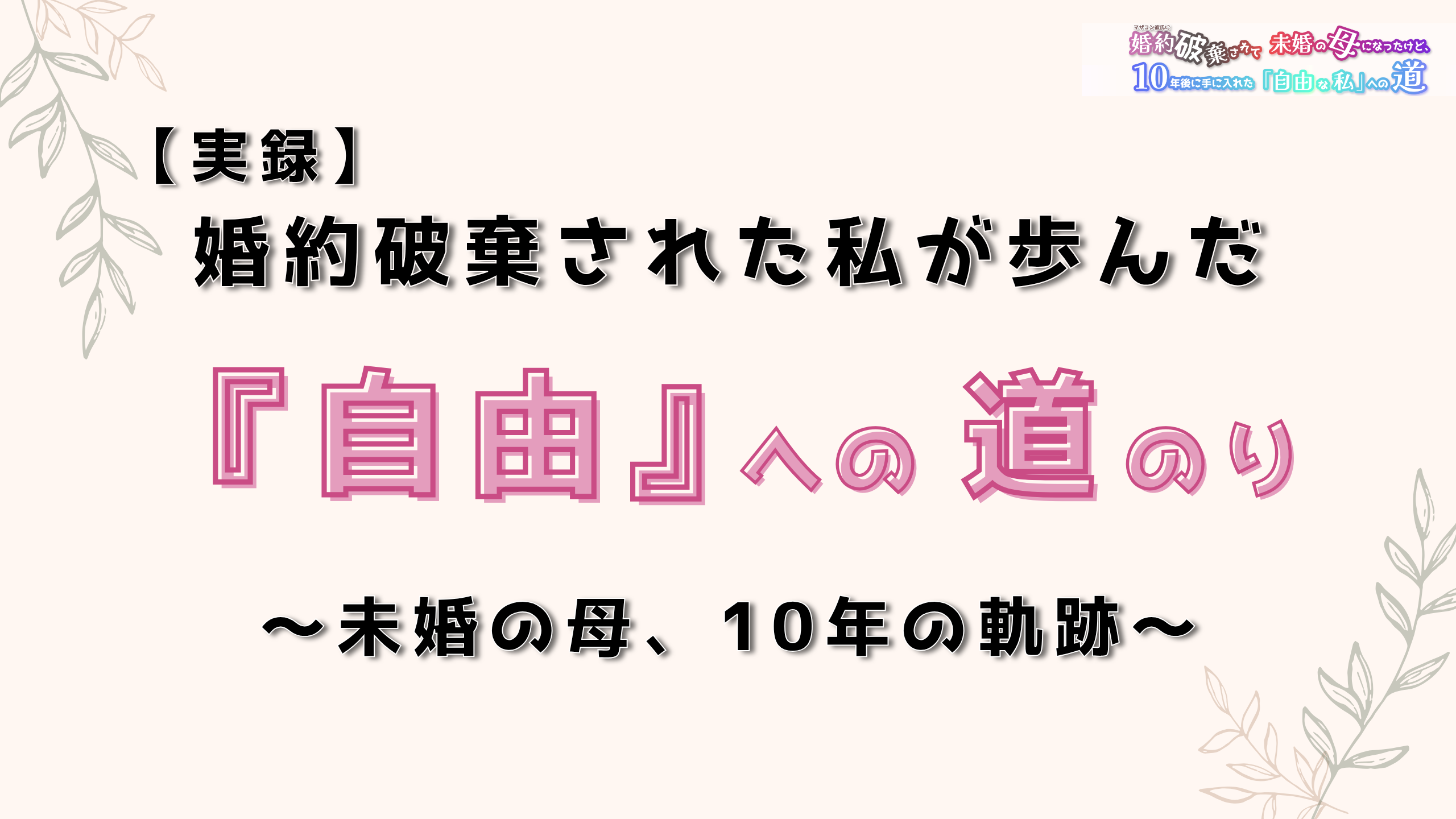婚約破棄された私を支える『児童扶養手当』 〜支えられることも、強さのひとつ〜
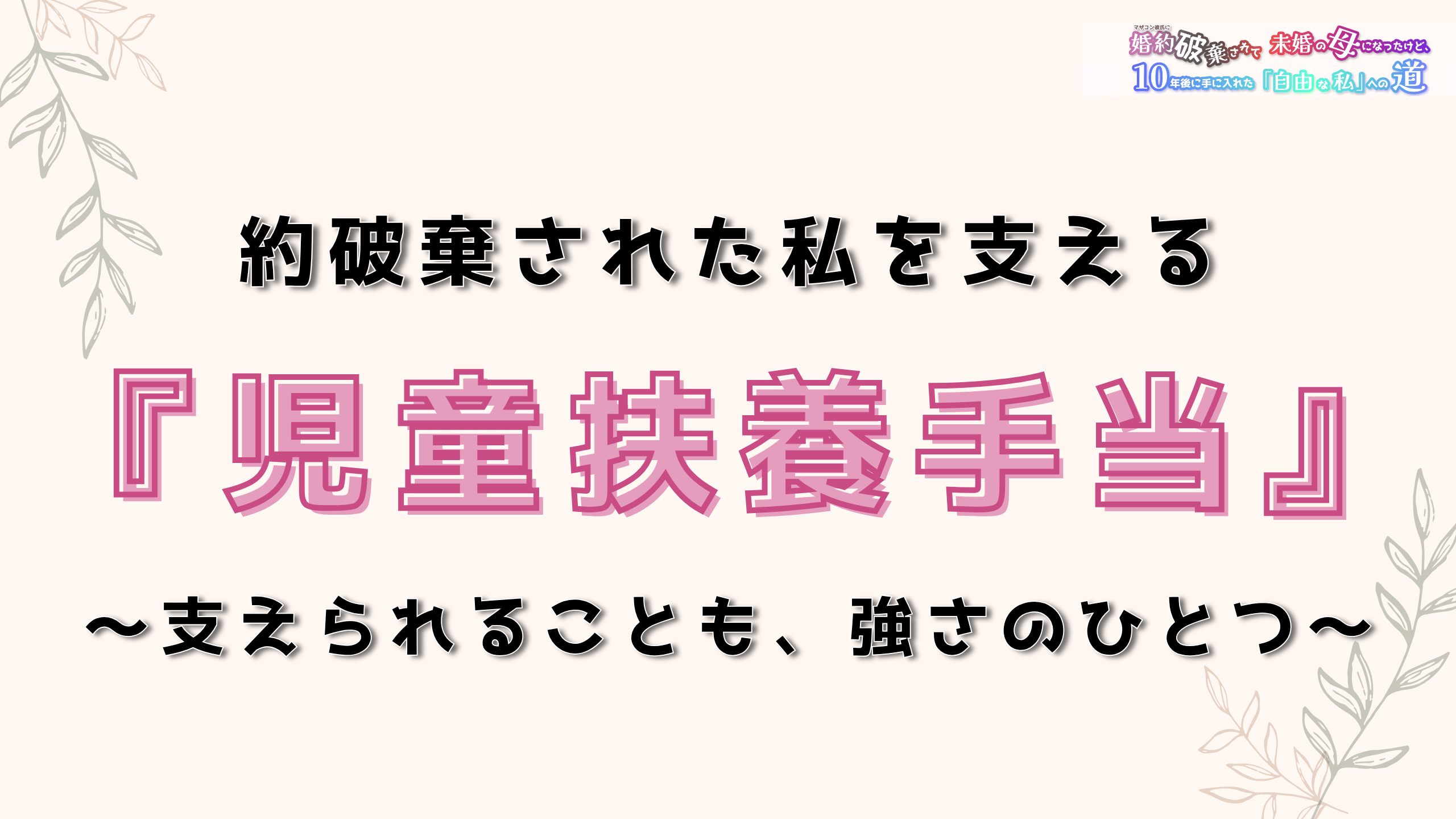

「母子手当」という言葉を聞いたことがありますか?
今は幅広く「ひとり親家庭」を支援する制度として、『児童扶養手当』という名称になっています。
今回は私が児童扶養手当を申請するまでの葛藤と、実際に申請することにした経緯、受け取ることで変化した気持ちのお話です。
はじめに:支援を受けることへの“後ろめたさ”
シングルマザーになったばかりの頃、私は「自分で選んだ道だから」と、児童扶養手当の申請をしていませんでした。
正直に言うと、この制度の存在自体は知っていましたが、正式名称および詳細を知ったのは子どもの出生届を提出したときでした。
窓口で「児童扶養手当の申請はされますか?」と聞かれて、私は反射的に「え、私は離婚してないです」と答えました。
「児童扶養手当は離婚した母子家庭のための制度」——そんな思い込みが、私の中にはあったのです。
申請するための書類一式を受け取って帰宅したものの、申請しないまま1年以上が過ぎていました。
そこには、こんな思いがずっと渦巻いていたのです。
「ちゃんと自立しなければ」
「自分で決めて母子家庭になったのに、支援を受けるのは甘えではないか」
そんな意地にも似た後ろめたさが、私の一歩を踏み出せなくしていました。

「“未婚”で勝手に産んだ“母”」なのに、もらっていいのかな…」という後ろめたさが拭えなかったんです。
でもある日、その思いを一変させる出来事がありました。
「税金で生きてるんでしょ?」—偏見の言葉が刺さった日
春の陽気に誘われ、子どもを一時保育に預けた後、久しぶりに一人の時間を楽しもうと入ったカフェでほっと一息ついていた時、見覚えのある女性に声をかけられました。
以前の職場の同僚である彼女とは、特別親しいわけではなかったけれど、お互い一人だったので相席することに。
まだ午後2時だというのに、ビールを飲んでいる彼女に少し違和感を感じながらも、私は近況など軽い会話を続けていましたが、彼女は唐突に言い出しました。
「実は私も離婚したいんだよね」
「離婚した方が自由だし、児童扶養手当ももらえるじゃない。今よりずっとましだと思うのよ」
彼女の話を聞きながら、私は複雑な気持ちになりました。
「あなたは一人でうらやましい」
「母子家庭っていいよねー。税金で暮らしてるんでしょ?うらやましい」
そう言われた瞬間、私の中で何かが凍りついたような感覚がありました。
言葉を返す余裕もなく、ただ愛想笑いを浮かべて彼女の顔を見つめることしかできませんでした。
「母子家庭」というだけで、“税金で楽して生きている”と決めつけられた現実に胸が痛み、同時に、社会にはこういう偏見が根強くあるのだと、改めて突きつけられた気がしました。
しばらく無言で彼女を見つめた後、私は静かにこう答えました。
「実は私、手当はもらってないの。申請していないから」
すると彼女は少し驚いた様子を見せ、「え、でももらえるんでしょ?もったいない!私が離婚したら絶対もらうわ」と言いました。
その後の会話の詳細は記憶にありません。
ただ、この場を早く離れたいという思いだけが強くなり、適当な理由をつけて席を立ちました。
カフェを出た後の私は複雑な気持ちでした。
悔しさと悲しさが入り混じったよくわからない感情。
でも不思議なことに、家に帰る頃には、この出来事が私の心に別の種類の変化を芽生えさせ始めていました。
「なぜ私は手当を受け取ることをためらっているのだろう?」
「子どものためにも、自分の意地より現実的な選択をすべきではないか」
一人で抱え込む苦しさを、誰も評価してくれない。
それなら、使えるものは使って、少しでも自分と子どもの生活を楽にする方が賢明ではないか。
そんな思考が芽生え始めたのです。

人のことを見下して、何を言ってもいいと思っている人ってたまにいませんか?
私は、メンタルによくないので積極的に離れます。
「よし、もらおう」—吹っ切れた瞬間とその後の心の変化
何の気なしに放たれた偏見に満ちた言葉が、皮肉にも私の心の殻を破るきっかけになりました。
「どうせ受け取っていると思われているなら、実際に受け取ってもいいのでは?」
“母子家庭”というレッテルだけで、決めつけられていた現実。
その一方で、実際には受け取る権利があるのに受け取っていない自分。
何のために我慢しているのだろう?
誰のための意地なのだろう?
家に帰り、引き出しの奥にしまってあった書類を取り出し、机に広げながら、
「よし、もらおう」
そう心に決めた瞬間、不思議と肩の力が抜けたのを今でも鮮明に覚えています。
まるで長い間背負っていた重荷を、やっと下ろすことを自分に許したような解放感がありました。
支援を必要とする人がいて、それを支える制度が整っている。
これは社会の仕組みとして当たり前のこと。医療保険や年金と同じ。
それなのに、なぜ自分だけが「もらってはいけない」と思い込んでいたのだろう?
「シングルマザー=かわいそう」「支援=施し」という世間の偏見を、知らず知らずのうちに自分も内面化していたのかもしれません。
後日、新たに取得した書類に記入しながら、少しずつ自分の考えが整理されていきました。
意地を張らず、素直に支援を必要としていることを認める。
それは「弱さ」ではなく、現実を直視する「強さ」なのだと。
支えられることを選択する勇気も、立派な強さなのだと、その時ようやく気づくことができました。

「この制度を使って、しっかり子育てをして、いつか私も誰かを支える側になろう」
そんな思いを胸に、窓口へと足を運んだのです。
もう、後ろめたさはありませんでした。
手続きは面倒だけど、子どものためにも乗り越えよう
扶養手当の申請は、正直に言って手間がかかります。
さらに初回だけでなく、必要書類を毎年提出する必要があります。
私の住む地域では、市役所または生活支援センターが窓口でしたが、提出書類も多く、不備があれば何度も足を運ぶことになります。
当時はメンタル的にも弱っていたので、担当者の些細な言葉にも傷ついたりしました。
具体的な確認事項の例
あくまで私の場合ですが、下記のような項目を確認されました。
- 生活状況に関する詳細な聞き取り
- 日々の生活費はどう賄っているのか
- 仕事の状況や収入
- 養育費に関する詳細な聞き取り
- 養育費の取り決めの有無
- 実際の受取状況
- 居住実態の確認
- 子ども以外の同居人の有無
- 居住開始時期
- 光熱費の請求書などの証明書類の提出
- 地域の民生委員との面談や自宅訪問
- 申請住所での実際の生活実態確認
- パートナー関係の確認
- 現在お付き合いしている方の有無
- 友人の例:「いる」と答えたら、パートナーからの生活支援の可否を確認されたそうです
パートナーがいたら対象外?
確認事項は、地域や担当の方によって異なるのかもしれないのですが、
現在お付き合いしている方の有無についての質問は意味が分かりませんでした。
「え、この状況でいると思うの?」って思いましたが、いろんな人がいますもんね。
私も聞かれましたし、友人の中には「います」と答えたところ、
「その方に生活の支援はしていただけないのかしら?」と返された子がいました。
…いやいや、なんで?
お付き合いをしているだけで、生活を支えてもらえる前提って、おかしくないですか?(笑)
もちろん、確認してくるくらいなので、制度上の確認が必要なのは理解しています。
でも、人との関係性やプライベートにまで踏み込まれるのは、正直しんどい瞬間もあるんです。
養育費をもらっていたら対象外?
最も緊張したのは、養育費に関する聞き取りでした。
担当者の質問に答えながら、二つの不安が心を支配していました。
「養育費を受け取っていたら、手当はもらえないのではないか」
「養育費ももらっているのに、さらに公的支援が必要だなんて、贅沢だと思われるのではないか」
特に後者については、世間からの目を気にしてしまう自分がいました。
でも、実際の制度は私の不安とは異なっていたのです。
担当者は下記の内容を丁寧に説明してくれました。
- 養育費の有無だけで支給の可否が決まるわけではない
- 児童扶養手当には所得制限がある
- 所得が一定額を超える場合、手当が減額または支給停止される
- 限度額は扶養親族の人数により異なる
- 手当の支給額は、児童の人数や受給者の所得によって異なる
つまり、養育費を受け取っていても、総合的な所得が基準額を超えなければ手当を受給できるのです。
養育費が十分な金額であれば、給料などの所得と合わせて、自然と所得制限にかかることもあるかもしれませんが、多くの場合、養育費だけでは子育てに必要な費用を賄いきれないという現実を、制度もしっかりと反映しているのだと感じました。
虚偽申告、ダメ!絶対!
担当者は続けて最も重要なことを伝えてくれました。
「申請書は、必ず正確に事実を記入してくださいね。後々、虚偽申告と判断されると、さかのぼって返還を求められることがあります」
優しい口調でしたが、言葉には明確な警告が含まれていました。
制度を正しく利用するためには、自分の申告に責任を持たなければならないという意識も強くなりました。

「どうせバレないから」と虚偽の申告を嬉々として報告している方が周りにいたとしても、絶対に真似しないようにしましょう。
ふと漏れた不利なことを密告される可能性はゼロではないです。
また児童扶養手当申請についての詳細は自治体によって異なるかもしれないので、必ずお住まいの自治体で確認してくださいね。
未婚の母でも、児童扶養手当は受け取れる
児童扶養手当を受け取れるのはどんな人?
ここまで、児童扶養手当の申請に対する葛藤や、実際の申請時のお話をしてきましたが、そもそもどんな人が受け取れるの?と疑問に思っている方のために少し調べてみました。
(※インターネット検索での情報なので、鵜呑みにせず、ご自身でもお調べください)
児童扶養手当は、ひとり親家庭やそれに準ずる家庭で、子どもを育てている方のための制度です。
以下のいずれかに該当し、かつ日本国内に住所がある場合、支給対象となる可能性があります。
- 父母が離婚し、どちらか一方が子どもを養育している
- 父または母が死亡している
- 父または母が重度の障害により養育が困難である
- 父または母の生死が明らかでない(行方不明など)
- 裁判所からDV保護命令が出ており、父または母と子どもが接触できない状態にある
- 父または母から1年以上育児放棄(遺棄)されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている(例:刑務所などに収容)
- 婚姻によらずに生まれた子どもを養育している(未婚の親)
- 父母の所在が不明で、祖父母などが代わりに子どもを養育している
以下のケースでは、手当の対象外となることがあります
- 保護者または子どもが海外に居住している場合
- 子どもが里親に委託されている場合
- 子どもが児童福祉施設に入所している場合(※母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)
※詳細は、お住まいの自治体や公式サイトなどで最新の情報を確認してください。
未婚の母や父子家庭(平成22年8月から)も制度の対象です。
児童扶養手当に関しては、性別に関係なく、また離婚だけでなく、配偶者の死亡、生死不明、障害、DV等による別居(平成24年8月から)などの場合も対象となるそうです。
つまり、この制度は”母子家庭を特別に優遇している制度”ではなく、「子どもを一人で育てる家庭全体を支えるための制度」なのです。

私は「児童扶養手当は、離婚した母子家庭のもの」と思い込んでいましたが、実際には、児童扶養手当の対象は幅広いですね。
「ひとり親」であることが重要な基準となりますが、制度をちゃんと理解していなかった私は、自分を“制度の外側”に置いてしまっていたました。
児童扶養手当はいくらもらえるの?
実際に「いくらもらえるの?」という声もよく聞きます。
児童扶養手当の金額は収入(所得)によって異なるため、人それぞれですし、年ごとに変動もあります。
児童扶養手当についてまとめてみましたが、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
児童扶養手当の支給額は、子どもの人数や、受給者(親や養育者)の所得額によって異なります。
所得に応じて「満額支給」または「一部支給」が行われ、子どもが増えるごとに加算額が支給される仕組みです。
- 児童が1人の場合
- 満額支給:月額44,140円
- 一部支給:月額10,410円〜44,130円
- 児童が2人の場合
- 上記に加え、**月額10,420円(満額)**が加算されます
- 一部支給の場合は、この加算額も所得に応じて減額されます
(月額5,210円〜10,410円)
- 児童が3人以上の場合
- 3人目以降の子ども1人につき、さらに**月額6,250円(満額)**が加算されます
- 一部支給の場合、月額3,130円〜6,240円の範囲で加算されます
※詳細は、お住まいの自治体や公式サイトなどで最新の情報を確認してください。

児童の人数、所得に応じて細かく設定されていますが、一覧表などはインターネット上で最新版を確認することができます。
よくわからない場合は、お住まいの自治体の窓口で相談してみるのもいいと思いますよ。
支えられることも、強さのひとつ
「支援制度=楽して得してる」
「優遇されていてずるい」
なんてイメージを持たれることもあるかもしれません。
でも、実際はそうではありません。
私たちは、制度のルールの中で、しっかり審査を受け、正当に支援を受けているのです。
だからこそ――
胸を張りましょう。
誰にも頼らず、ひとりで全部抱え込むことだけが「自立」ではありません。
助けを受けることを選べる強さも、誇っていいと思うんです。
誰のための支援なのかを考える
児童扶養手当の制度を調べると、子どもが健やかに育つ環境を守ることに焦点を当てているからこそ、親の状況や背景に関わらず支援の手が差し伸べられるのだと理解できました。
それなのに、私のような誤解や社会に根強く残る偏見のせいで、最初から申請を諦めてしまう人が少なからずいるのではないかと感じています。
実際、制度について調べ始めた頃、インターネット上で「手当をもらっている=怠けている」というような心ない書き込みを目にしたこともあります。
あるいは、「未婚なのに子どもを産んだ自分が、公的支援を受ける資格があるのだろうか」と自問自答する方もいるかもしれません。私自身、そうでした。
しかし、冷静に考えてみれば、この制度の根底にあるのは「子どもの権利」です。
親の状況がどうであれ、子どもには健やかに育つ権利がある。
その権利を守るために、社会全体で支えていこうという考え方が基本にあるのだと思います。
私の場合、申請のきっかけは皮肉にも他人の偏見でしたが、実際に調べてみると、この制度の意義を考え直すきっかけにもなりました。

もし私のような誤解をしている方がいれば、ぜひ一度、お住まいの自治体の窓口で相談してみることをおすすめします。
子どものために使える制度は賢く利用するという選択も、立派な親としての責任の果たし方だと思います。
「満額もらわないと損」ではなく、「支えられている間にどう生きるか」
中には、「満額もらうために働き方を抑えている」という人もいます。
もちろん、その選択を否定するつもりはありません。
働く時間を抑えた分、他のもの、たとえば大切な“時間”などを得ることができますしね。
でも私は、こう思っています。
「もらえる金額に合わせて生きる」のではなく、
「支えられている間に、自立する力を育てていく」ことが、とても大切なことだと。
児童扶養手当はずっと受け取れるものではありません。
いずれ子どもは大きくなり、制度の対象から外れる日がやってきます。
そのとき、自分の働き方や収入を制限したままだったら――
困るのは、自分自身なんですよね。
「満額もらえてよかった」ではなく、
「あのとき制度に支えられて、前に進めた」って言える未来をつくりたい。

今は支えてもらいながら、未来の自分の生活を整えていくことは、
しなやかで強い生き方だと思います。
最後に:迷っているあなたへ
「私も申請していいのかな」と迷っている方がいるかもしれません。
そんなあなたに、私はこう伝えたいです。
「迷う気持ち、すごくよくわかります」
私もそうだったから。
でも今だから言えます。
“支えてもらう時間”があったからこそ、私は前に進めました。
あなたの努力が、誰にも見えていないなんてことはありません。
支援を受けることは、甘えではありません。
社会の制度に支えられる時間があるからこそ、未来の自分を整える準備ができる。
助けを受けながら前に進むことだって、立派な“自立”のかたちなんです。
いつか制度の対象外になる日が来ても――
そのときに、「ちゃんと準備してこれた」と思える自分でいられるように。
だからこそ、今この瞬間に、支えてもらう選択があってもいい。
その一歩を、あなたにも踏み出してほしいと思います。

支援制度は、あなたの人生を“楽にする”ためではなく、
あなたと子どもが“安心して生きる”ためにあるんです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
このブログでは、これからも私の経験から学んだことをお届けしていきます。
少しでもお役に立てたら嬉しいです♪
また次回の記事でお会いしましょう!